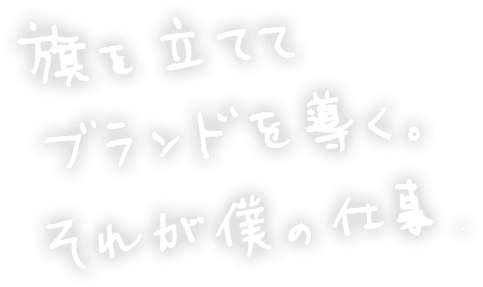
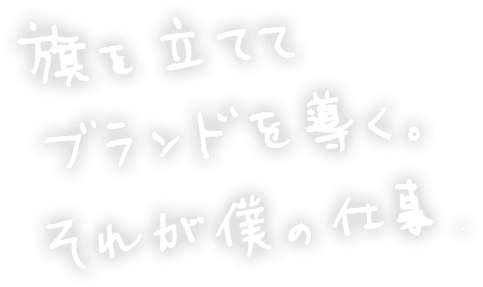
2014年入社

僕の中川政七商店でのキャリアは、5 年前の小売課のアルバイトからはじまりました。当時、新卒で入社した人材系企業で営業として働いていたんですが、何気なくつけたテレビで流れてきた、日本各地のつくり手さんに対してコンサルティングを行う会⾧の中川の様子。一瞬で、「ここだ!」と思ってしまったんです。

雑貨や工芸について造詣が深かったわけでもなかったけれど、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンと、ビジョンを体現するその様子に、強烈に惹かれるものがありました。中川の映像が終わった瞬間、中川政七商店の採用サイトを開いていました。
小売課で入社したのは、その時に募集していたのが、小売課のアルバイトだけだったということが理由です。未経験とかアルバイト採用ということには、ためらいはありませんでした。当時20 代前半と若かったから無茶ができたのかも知れないけど、この直感は間違いではなかったと、今も思っています。

スーパーバイザーとしての経験は2 年ほどになり、今は6 店舗を担当していますが、小売課の大半の後方業務を、3 年ほど積んだ経験が、今の自分のことを支えてくれているんです。
スーパーバイザーというのは、店舗スタッフに店⾧、エリアリーダーと、店舗を運営するスタッフたちを支える仕事だと考えています。当然、店舗出身者が就くことが多い。中川政七商店の場合もそうで、僕以外は店⾧として素晴らしい実績を残してきた、スペシャリストばかりです。

でも最初から不安はありませんでした。僕は店舗出身ではないから、従来のスーパーバイザーにはなれないことはわかっていた。だからこそお店のことは、店⾧やエリアリーダーのことを信じて任せる。ただ、システムや物流業務などの後方業務、数値管理に関しては、僕が突き抜ける。そうやって、みんなが現場に集中できる環境をつくろうと思ったんです。
現場を知らないからこそ、できることかもしれないですが、売り場のことはみんな、バックヤードのことは僕。得意な人が得意なことをやる方が、絶対にいいから。でも、任せるからといって放置はしません。お店には顔を出すし、アルバイトさんを含めてみんなに声をかける。みんなのことを気にかけて、ちゃんと見守っているスーパーバイザーでありたいからです。

一方で、僕だけが責任を持ってやるべきことも明確にあります。それはブランドがどこへ進むのかという、方向性を示すこと。旗を立てることです。
例えば僕が担当するブランドのひとつ、「日本市」。日本各地の地産地消のお土産をお客様にご紹介することがミッションです。僕がスーパーバイザーになってからいつもみんなに伝えているのは、「この土地でしか買えないお土産をちゃんと販売しよう」ということ。

お土産物以外も店頭には並ぶので、行楽シーズンが近づけはバックや服飾小物は手にとっていただきやすいんです。店頭に立ってお客様と接するスタッフたちは、お客様が喜んでくださることが何より嬉しいので、どうしてもシーズン商品を中心に置きたくなるもの。でもそれは、日本市というブランドの方針としては違います。
短期的な売り上げではなく、僕たちの目指すところはどこなのかを大切に、物事を判断しなければいけません。でも、こういう判断が、スーパーバイザーとして一番難しい仕事だと思います。数字だけ見れば服飾小物に力を入れるべきだけど、ブランドの方向性とは違う。そのバランスをどう取るのか。難しいからこそ、きちんと納得できるまで、店⾧とは話をします。
一方で、目先の数字を負わなくても、やることをしっかりやっていれば、結果は必ずついてくるとも思っているんです。万が一、上手くいかないことがあれば、その時は僕が責任を取ればいい。それだけの覚悟はあります。

でも、上手くいかないことなんて、そうありません。店⾧自身が、どんなお店にしたいのかをきちんと描けていれば、絶対に大丈夫なんです。僕の役割はブランドの旗を立てることだとお話をしましたが、店⾧の役割は、店舗の旗を立てることだと思っています。

そしてその旗は、色々であっていい。「みんなが働きやすい店舗」でもいいし、「もっとたくさんの方に知っていただく店舗」でもいい。もちろん「最も売上げをつくる店舗」でもいいかもしれません。同じブランドでほぼ同じ商品が並ぶお店であっても、お店ごとに雰囲気が違っていいんです。お客様に、お店の個性の違い(=店⾧の個性の違い)まで気づいていただくところまでいけたとしたら、ブランドが強く成⾧している証です。
店舗毎に目指したいお店の像があって、そこに向けてスタッフは日々頑張っている。そのことを僕が誰よりも信じているから、心配はありません。もし数字が心配になりはじめたら、店⾧たちのことを信じられなくなった証拠ですね。
つくり手の皆さんの思いのつまった商品を扱う場所が、店舗。スタッフたちが生き生きと、そのストーリーをお客様にお話しすることで、つくり手さんのファンが増えていくことこそが、工芸を元気にすることにつながると、僕はずっと信じています。
5年前、テレビ越しに中川から受けた衝撃は薄れるどころか、自分がその一端を担える仕事ができている。そう実感できる現在が、とても嬉しく幸せなんです。